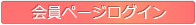ホーム » 植木協会の取組み » 緑育出前授業
緑育
緑は人類や動物、全ての生き物にとってかけがえのない存在です。
しかし、緑は地球規模で無くなっています。それではどうすれば良いのでしょう。
まずは「木を育て、緑は育てることが出来るということ」 を私たちが知ることではないでしょうか。それがすべての始まりとなり、緑育となるのです。
これを子どもたちに伝えることが私たちの 使命ではないでしょうか。
 |
お問い合わせ先
一般社団法人 日本植木協会
〒107-0052 東京都港区赤坂6-4-22 三沖ビル3F
TEL 03-3586-7361 FAX 03-3586-7577
「緑育ってなにするの」
緑育は緑に親しみをもってもらうために、緑の育ち方、環境とのかかわりを体感してもらう授業です。
「誰がしてくれる授業なんですか」
学校の卒業生で植木の生産や流通、販売、工事、管理といった仕事をしている方たちです。もし、卒業生がいなければ、学校の近くや県内の方が対応します。
「地元の植木屋さんが授業をするの?」
学校に通う子どもたちの保護者が授業をすることで、子どもたちは仕事により理解を深めることができます。そしてキャリア教育の側面ももっています。
緑育は緑に親しみをもってもらうために、緑の育ち方、環境とのかかわりを体感してもらう授業です。
「誰がしてくれる授業なんですか」
学校の卒業生で植木の生産や流通、販売、工事、管理といった仕事をしている方たちです。もし、卒業生がいなければ、学校の近くや県内の方が対応します。
「地元の植木屋さんが授業をするの?」
学校に通う子どもたちの保護者が授業をすることで、子どもたちは仕事により理解を深めることができます。そしてキャリア教育の側面ももっています。
1.この木なんの木?
学校や、近くの公園など授業のフィールドになる場所の木を事前に調べて、その木 に関する問題を作成してオリエンテーリングのように木の名前を答えていきます。
2.樹木名板取り付け
チームに分かれて、木の名前や特徴を調べ、各チームが発表してから、オリジナルの樹名板を取り付けます。
3.グリーンウェイブ
国連が奨めるグリーンウェーブをサポートします。5月22日、午前10時に世界中で木 を植えて緑の"波〜ウェーブ"を作ります。
4.植木の育て方
花は育てたことはあるけど、木は植えたことがない子どもたちに、植木の育て方を教えます。
5.その他
地元の植木屋さんが、学校とお話しさせて頂き、オリジナルの授業を作ります。
※これらの授業での資材、 講師派遣等の費用は 社団法人日本植木協会が負担します。
学校や、近くの公園など授業のフィールドになる場所の木を事前に調べて、その木 に関する問題を作成してオリエンテーリングのように木の名前を答えていきます。
2.樹木名板取り付け
チームに分かれて、木の名前や特徴を調べ、各チームが発表してから、オリジナルの樹名板を取り付けます。
3.グリーンウェイブ
国連が奨めるグリーンウェーブをサポートします。5月22日、午前10時に世界中で木 を植えて緑の"波〜ウェーブ"を作ります。
4.植木の育て方
花は育てたことはあるけど、木は植えたことがない子どもたちに、植木の育て方を教えます。
5.その他
地元の植木屋さんが、学校とお話しさせて頂き、オリジナルの授業を作ります。
※これらの授業での資材、 講師派遣等の費用は 社団法人日本植木協会が負担します。
植木に携わる仕事を通し私たちは幸せを感じています。木は人間以上に長く生き、その時々の人間の想いを次の世代に伝えてくれます。
その想いは、花となって春の訪れを伝え、強い日差しに木陰を作り一時の涼しさを与え、紅葉に恵みの訪れを知らせ、木々の葉を落として冬の日の暖かさを教えてくれます。 これら植木の多くは、人が次の世代のために植え、育てたものなのです。
私たちは、そんな人間の自然な営みを伝え育てていきたいと考えています。
その想いは、花となって春の訪れを伝え、強い日差しに木陰を作り一時の涼しさを与え、紅葉に恵みの訪れを知らせ、木々の葉を落として冬の日の暖かさを教えてくれます。 これら植木の多くは、人が次の世代のために植え、育てたものなのです。
私たちは、そんな人間の自然な営みを伝え育てていきたいと考えています。
現在、地球規模での環境悪化、その最大の問題であるCO2の吸収に有効な唯一の方策として挙げられるのが、植樹によって樹木がCO2を固定化することです。
そういった現実にありながら、現在の日本国民の多くは知識としての理解もさることながら、行動が伴っていないのが実態です。
私たち、緑に係わる仕事を生涯の使命とするものは、この緑の大切さを伝え、育んでいかなければなりません。
私たちは、この伝え育む活動「緑育」を時代の要求が無くなるまで行い、社会に貢献し、使命を全うします。
そういった現実にありながら、現在の日本国民の多くは知識としての理解もさることながら、行動が伴っていないのが実態です。
私たち、緑に係わる仕事を生涯の使命とするものは、この緑の大切さを伝え、育んでいかなければなりません。
私たちは、この伝え育む活動「緑育」を時代の要求が無くなるまで行い、社会に貢献し、使命を全うします。
ホーム » 植木協会の取組み » 緑育出前授業