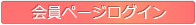| 北海道 |
| 青森県 |
| 岩手県 |
| 宮城県 |
| 秋田県 |
| 山形県 |
| 福島県 |
| 茨城県 |
| 栃木県 |
| 群馬県 |
| 埼玉県 |
| 千葉県 |
| 東京都 |
| 神奈川県 |
| 新潟県 |
| 富山県 |
| 石川県 |
| 福井県 |
| 山梨県 |
| 長野県 |
| 岐阜県 |
| 静岡県 |
| 愛知県 |
| 三重県 |
| 滋賀県 |
| 京都府 |
| 大阪府 |
| 兵庫県 |
| 奈良県 |
| 和歌山県 |
| 鳥取県 |
| 島根県 |
| 岡山県 |
| 広島県 |
| 山口県 |
| 徳島県 |
| 香川県 |
| 愛媛県 |
| 高知県 |
| 福岡県 |
| 佐賀県 |
| 長崎県 |
| 熊本県 |
| 大分県 |
| 宮崎県 |
| 鹿児島県 |
| 沖縄県 |
・放射能汚染対策に関して東京電力(株)本社からの回答がありました(2012/8/2更新)
・放射能汚染に対する除染関係ガイドラインが環境省、厚生労働省から出ています(2012/1/31更新)
・放射能汚染対策に関して東京電力(株)本社へ要望(2012/1/31更新)
・「花とみどりの復興支援ネットワーク」への参加・協力の要請について(2011/12/05更新)
・東日本大震災「花とみどりの復興支援ネットワーク」設立 ホームページは近日公開予定。10/27記者発表資料はこちら (2011/10/28更新)
・原子力損害の判定等に関する中間指針について (2011/08/17更新)
・放射性セシウムを含む堆肥・土壌改良材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について(農林水産省通知) (2011/08/11更新)
・東日本大震災義援金募集結果について(2011/08/1更新)
・高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について (2011/7/29更新)
・夏期の電力需給対策について (2011/7/13更新)
・東日本大震災の復興支援について (2011/6/10更新)
・会員限定情報にて掲載中!福島第一原子力発電所事故に関連した緑化木等の出荷に当たってのQ&A(林野庁作成)(2011/6/1更新)
・放射能汚染に対する除染関係ガイドラインが環境省、厚生労働省から出ています(2012/1/31更新)
・放射能汚染対策に関して東京電力(株)本社へ要望(2012/1/31更新)
・「花とみどりの復興支援ネットワーク」への参加・協力の要請について(2011/12/05更新)
・東日本大震災「花とみどりの復興支援ネットワーク」設立 ホームページは近日公開予定。10/27記者発表資料はこちら (2011/10/28更新)
・原子力損害の判定等に関する中間指針について (2011/08/17更新)
・放射性セシウムを含む堆肥・土壌改良材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について(農林水産省通知) (2011/08/11更新)
・東日本大震災義援金募集結果について(2011/08/1更新)
・高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について (2011/7/29更新)
・夏期の電力需給対策について (2011/7/13更新)
・東日本大震災の復興支援について (2011/6/10更新)
・会員限定情報にて掲載中!福島第一原子力発電所事故に関連した緑化木等の出荷に当たってのQ&A(林野庁作成)(2011/6/1更新)
平成24年1月10日東京電力(株)本社において、水城会長等三役は、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染に関して、要望書を提出していたが、平成24年6月6日、大略、下記のような回答があった。
? 避難会員が行う損害賠償事務の手続きの簡素化を図るとともに、速やかな支払いを行うことについて
(回答)
出来る限り簡素化を図るとともに、親切・丁寧に対応し、請求の支払いも目標期間内に完了している。
? 会員が負担した放射能汚染に起因した費用について、適切な補償を行うことについて
(回答)
政府の中間指針に沿って、土壌の汚染状況や原子力発電所との距離を考慮して、福島、茨城、栃木の3県で産出された植木の検査費用については、原発事故との相当因果関係にある損害と考えられ、それ以外の都道府県で産出された植木については、相当因果関係にある損害にはあたらないと考えている。
? 会員が行う放射能汚染に係る対応について、人的・物的な支援を行うこと。特に、放射線量測定機器の貸与又は購入助成をすることについて
(回答)
当社も種々の取組に相当量の測定機材を使用しており、機材が不足していることから、要請に応えることは困難な状況にある。
? 貴社自らが、率先して、緑化樹木等非食用物の放射能汚染に対する市民等の不安を解消するための広報を適切に行うことについて
(回答)
今後の情報発信や広報活動のあり方を検討するに当たって考慮する。
? 避難会員が行う損害賠償事務の手続きの簡素化を図るとともに、速やかな支払いを行うことについて
(回答)
出来る限り簡素化を図るとともに、親切・丁寧に対応し、請求の支払いも目標期間内に完了している。
? 会員が負担した放射能汚染に起因した費用について、適切な補償を行うことについて
(回答)
政府の中間指針に沿って、土壌の汚染状況や原子力発電所との距離を考慮して、福島、茨城、栃木の3県で産出された植木の検査費用については、原発事故との相当因果関係にある損害と考えられ、それ以外の都道府県で産出された植木については、相当因果関係にある損害にはあたらないと考えている。
? 会員が行う放射能汚染に係る対応について、人的・物的な支援を行うこと。特に、放射線量測定機器の貸与又は購入助成をすることについて
(回答)
当社も種々の取組に相当量の測定機材を使用しており、機材が不足していることから、要請に応えることは困難な状況にある。
? 貴社自らが、率先して、緑化樹木等非食用物の放射能汚染に対する市民等の不安を解消するための広報を適切に行うことについて
(回答)
今後の情報発信や広報活動のあり方を検討するに当たって考慮する。
福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染に対して、除染等の措置に対するガイドラインが環境省、厚生労働省から出ていますので、紹介します。
? 環境省「除染関係ガイドライン」(平成23年12月 第1版)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることをめざし、除染を進めて行くことになっていますが、その過程を具体的にわかりやすく説明するため、環境省では、除染関係ガイドラインを策定しています。
全体の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
このガイドラインは四編に分かれており、?「汚染状況重点調査地域内における環境の汚染の状況の調査測定方法のガイドライン」、?「除染等の措置に係るガイドライン」、?「除去土壌の収集及び運搬に係るガイドライン」及び?「除去土壌の保管に係るガイドライン」となっていますが、?の「除染等の措置に係るガイドライン」のうち、?.土壌汚染等の措置、?.草木の汚染等の措置について(2-54頁〜2-88頁)を紹介します。
? 厚生労働省「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月)
放射性物質の除染等の作業に従事する労働者の放射線障害を防止するため、除染等業務に従事する労働者に対して、必要な防護措置が実施される必要があり、厚生労働省からそのためのガイドラインを策定し、林野庁長官を通じて、本協会会長にも除染等の作業を行う農林業従事者等へも周知するよう依頼があったものです。
本ガイドラインは、厚生労働省令の除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層、的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的としています。
特措法に規定する除染特別地域等内における放射能汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる業務を行う事業者に適用することになっていますが、それ以外の事業者で自らの敷地や施設等において除染等の作業を行う事業者、伐木、枝打ち、土壌の掘削等の作業を行う事業者又は除染特別地域等でない場所で除染等作業を行う事業者は、第3の被ばく線量管理、第5の汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置、第6の労働者教育等のうち、必要な事項を実施すること。除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティアについても同様とすることが望ましいこととされています。
林野庁長官の通達文およびガイドラインの概要はこちらをご覧ください。
全体の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
? 環境省「除染関係ガイドライン」(平成23年12月 第1版)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることをめざし、除染を進めて行くことになっていますが、その過程を具体的にわかりやすく説明するため、環境省では、除染関係ガイドラインを策定しています。
全体の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
このガイドラインは四編に分かれており、?「汚染状況重点調査地域内における環境の汚染の状況の調査測定方法のガイドライン」、?「除染等の措置に係るガイドライン」、?「除去土壌の収集及び運搬に係るガイドライン」及び?「除去土壌の保管に係るガイドライン」となっていますが、?の「除染等の措置に係るガイドライン」のうち、?.土壌汚染等の措置、?.草木の汚染等の措置について(2-54頁〜2-88頁)を紹介します。
? 厚生労働省「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月)
放射性物質の除染等の作業に従事する労働者の放射線障害を防止するため、除染等業務に従事する労働者に対して、必要な防護措置が実施される必要があり、厚生労働省からそのためのガイドラインを策定し、林野庁長官を通じて、本協会会長にも除染等の作業を行う農林業従事者等へも周知するよう依頼があったものです。
本ガイドラインは、厚生労働省令の除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層、的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的としています。
特措法に規定する除染特別地域等内における放射能汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる業務を行う事業者に適用することになっていますが、それ以外の事業者で自らの敷地や施設等において除染等の作業を行う事業者、伐木、枝打ち、土壌の掘削等の作業を行う事業者又は除染特別地域等でない場所で除染等作業を行う事業者は、第3の被ばく線量管理、第5の汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置、第6の労働者教育等のうち、必要な事項を実施すること。除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティアについても同様とすることが望ましいこととされています。
林野庁長官の通達文およびガイドラインの概要はこちらをご覧ください。
全体の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
文部科学省に設けられた原子力損害賠償紛争審査会は、東京電力(株)福島原子力発電所事故による被害者と東京電力(株)との損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成のため、平成23年8月5日、「東京電力(株)が賠償すべき損害」についての中間指針を示しました。
中間指針は、原子力発電所事故が収束していない中で、賠償すべき損害として類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものです。したがって、中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得ます。また、賠償対象として示されたものであっても、個別の事情によっては、対象とならない場合もあり得ます。
中間指針は、賠償すべき損害と認められる一定の範囲の損害類型を示していますが、具体的には、(1)「政府による避難等の指示等に係る損害」、(2)「政府による航行危険区域等及び飛行禁止区域の設定に係る損害」、(3)「政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害」、(4)「その他の政府指示等に係る損害」、(5)「いわゆる風評被害」、(6)「いわゆる間接被害」、(7)「放射線被曝による損害」を対象とし、更に、(8)「被害者への各種給付金等と損害賠償金との調整」や、(9)「地方公共団体の財産的損害」についても示しています。
被災地域における当協会福島県支部会員が対象となる損害の内容ついては、大きくは次の2つになっています。
(1) 政府指示等の対象地域内の会員については、「政府による避難等の指示等に係る損害」が対象となりますが、それについては、避難区域や屋内退避区域等における避難費用、一時立入費用、帰宅費用、生命身体的損害、精神的損害、営業損害等について示されています。
(2) 政府指示等の対象外地域の会員については、「いわゆる風評被害」が対象となりますが、それについては、風評被害の一般的な基準を示し、類型化された業種について、専門委員による詳細な被害の実態調査結果を踏まえ風評被害の範囲を明示しています。また、類型化できない個別の被害については、一般的基準に照らし、個別に相当因果関係を立証することになっています。
農林漁業・食品産業に係る風評被害では、緑化樹木については、特に明記されませんでしたが、「その他の農林産物(木材等)」のなかで、福島県内について風評被害の存在が認められています。
なお、「中間指針」の本文は、文部科学省ホームページの原子力損害賠償紛争審査会のページに掲載されています。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/
afieldfile/2011/08/17/1309452_1_2.pdf)
中間指針は、原子力発電所事故が収束していない中で、賠償すべき損害として類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものです。したがって、中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得ます。また、賠償対象として示されたものであっても、個別の事情によっては、対象とならない場合もあり得ます。
中間指針は、賠償すべき損害と認められる一定の範囲の損害類型を示していますが、具体的には、(1)「政府による避難等の指示等に係る損害」、(2)「政府による航行危険区域等及び飛行禁止区域の設定に係る損害」、(3)「政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害」、(4)「その他の政府指示等に係る損害」、(5)「いわゆる風評被害」、(6)「いわゆる間接被害」、(7)「放射線被曝による損害」を対象とし、更に、(8)「被害者への各種給付金等と損害賠償金との調整」や、(9)「地方公共団体の財産的損害」についても示しています。
被災地域における当協会福島県支部会員が対象となる損害の内容ついては、大きくは次の2つになっています。
(1) 政府指示等の対象地域内の会員については、「政府による避難等の指示等に係る損害」が対象となりますが、それについては、避難区域や屋内退避区域等における避難費用、一時立入費用、帰宅費用、生命身体的損害、精神的損害、営業損害等について示されています。
(2) 政府指示等の対象外地域の会員については、「いわゆる風評被害」が対象となりますが、それについては、風評被害の一般的な基準を示し、類型化された業種について、専門委員による詳細な被害の実態調査結果を踏まえ風評被害の範囲を明示しています。また、類型化できない個別の被害については、一般的基準に照らし、個別に相当因果関係を立証することになっています。
農林漁業・食品産業に係る風評被害では、緑化樹木については、特に明記されませんでしたが、「その他の農林産物(木材等)」のなかで、福島県内について風評被害の存在が認められています。
なお、「中間指針」の本文は、文部科学省ホームページの原子力損害賠償紛争審査会のページに掲載されています。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/
afieldfile/2011/08/17/1309452_1_2.pdf)
東日本大震災により、東京電力及び東北電力管内の供給量は大幅に減少しており、今後、夏に向けて、電力の需給バランスが悪化する見込みであることから、政府の電力需給緊急対策本部において「夏期の電力需給対策について」が決定されました。
同対策では、大口需要者(契約電力500KW以上)、小口需要者(契約電力500KW未満)、家庭とも均一に使用最大電力を15%抑制することを目標としており、電力需要者全員の具体的な節電行動の必要性が協調されています。
そのうち、小口需要者については、照明・空調設備の節電、営業時間の短縮・シフト、夏期休業の設定・延長・分散化等の具体的な節電計画を自主的に策定し、取り組むよう要請しています。
また、林野庁長官からも当協会会長宛に「夏期の電力需給対策に伴う節電実行計画の策定の要請について」及び「西日本5社の今夏の需給対策について」により節電実行計画の策定及び経済活動に支障を与えない範囲での節電に取り組むよう要請がありました。
当協会の会員では、電力の大口需要者は少なく、大多数が小口需要者であり、事業に係る電力需要についてもそれほど大きいものではありませんが、節電の主な対象としては、事務所・圃場休憩所での照明・空調設備の節電、圃場での潅水施設の節電(抑制対象時間帯(9時〜20時)以外の早朝に散水することが多い)等があります。
当協会会員は、従来からも事務所等の冷房の設定温度(28度以上)の遵守や支障のない範囲での照明の消灯・減灯に取り組んでいるところですが、この夏期の電力需給の状況に鑑み、東日本地域の会員は政府(資源エネルギー庁)の「節電行動計画の標準フォーマット」等を活用して「節電行動計画」を自主的に策定するとともにその実行を通じて使用電力の抑制に積極的に取り組み、また、西日本地域の会員もピーク期間・時間帯における使用電力の抑制に積極的に取り組むなど一層の節電に協力するようお願いします。
同対策では、大口需要者(契約電力500KW以上)、小口需要者(契約電力500KW未満)、家庭とも均一に使用最大電力を15%抑制することを目標としており、電力需要者全員の具体的な節電行動の必要性が協調されています。
そのうち、小口需要者については、照明・空調設備の節電、営業時間の短縮・シフト、夏期休業の設定・延長・分散化等の具体的な節電計画を自主的に策定し、取り組むよう要請しています。
また、林野庁長官からも当協会会長宛に「夏期の電力需給対策に伴う節電実行計画の策定の要請について」及び「西日本5社の今夏の需給対策について」により節電実行計画の策定及び経済活動に支障を与えない範囲での節電に取り組むよう要請がありました。
当協会の会員では、電力の大口需要者は少なく、大多数が小口需要者であり、事業に係る電力需要についてもそれほど大きいものではありませんが、節電の主な対象としては、事務所・圃場休憩所での照明・空調設備の節電、圃場での潅水施設の節電(抑制対象時間帯(9時〜20時)以外の早朝に散水することが多い)等があります。
当協会会員は、従来からも事務所等の冷房の設定温度(28度以上)の遵守や支障のない範囲での照明の消灯・減灯に取り組んでいるところですが、この夏期の電力需給の状況に鑑み、東日本地域の会員は政府(資源エネルギー庁)の「節電行動計画の標準フォーマット」等を活用して「節電行動計画」を自主的に策定するとともにその実行を通じて使用電力の抑制に積極的に取り組み、また、西日本地域の会員もピーク期間・時間帯における使用電力の抑制に積極的に取り組むなど一層の節電に協力するようお願いします。
3月11日に発生した東日本大震災は、発生後3ヵ月を経過してもなお、被災状況の全容が完全に把握できないほどの状況で、史上まれにみる広範囲にわたる激甚災害となりました。
この未曾有の大災害に対して、造園・環境緑化関係団体では、それぞれ様々な復興支援活動を準備していますが、その動きとしては、現在のところ、以下のとおりです。
1.当協会の被災会員に対する支援活動
(1) 協会では、会長等三役が被災会員のお見舞と激励のため現地に伺い、その後、顧問や林野庁に状況を説明して今後の対処についての協力をお願いしてきました。
(2) 理事会の決議により、当協会としては、甚大な被災会員5社園に対しては、協会から「お見舞金」贈呈及び年度会費の免除を実施する他、会員の皆様から義援金を募集することにしましたが、現在、2,191千円の義援金の拠出をいただいております。集まった義援金の配分等については7月の理事会で決定する予定になっています。
(3) 原発事故に係る補償に関しては、避難に伴う営業の損失や風評被害の賠償について、現在、政府の原子力損害賠償紛争審査会で検討中ですが、農林水産省でも、農林水産業等の原子力損害賠償請求を円滑に進めるため、関係県、農林水産業関係団体等からなる「東京電力福島原子力発電所事故に係る連絡会議」を設置しています。
(4) 当協会では、林野庁、連絡会議等の情報を逐次被災会員に提供するとともに、被災会員からの要望や情報を聴取し林野庁に伝える等林野庁と連携して被災会員に対する支援を続けて行くことにしています。
(5) 原発事故の発生に伴い、緑化木等の販売に係る風評被害の報告が協会に寄せられていますが、この度、林野庁から緑化木等の出荷に当たっての留意事項等としてQAが会員限定情報内で別掲しているとおり示されました。
2.造園・環境緑化関係団体の支援活動
(1) 造園・環境緑化関係団体による被災地の現地調査については、既に、日本造園学会や公園緑地協会で実施され、それぞれ報告(下記のURLで内容等が参照できます。)されています。
(2) 花と緑に係わる業界関係者等が連携協力して被災地域の復興活動事業を支援するため、造園関係団体が中心となった「(仮称)東日本大震災「花とみどり」の復興支援ネットワーク検討会議」及び花き関係の団体が中心となった「東日本大震災関連地域の花と緑による復旧・復興支援活動情報連絡会議」がそれぞれ立ち上げられています。
(3) このうち、造園関係団体が中心となった「ネットワーク検討会議」の検討状況については、
ア 参加団体が、それぞれの支援活動について情報交換をしました。
イ 地方公共団体からの具体的な支援要望を聴取したところでは、1:花苗、球根、肥料、土、スコップ、プランター等のガーデニング用品、2:街路樹や公園への苗木提供、3:サッカーボール等の提供、4:公園遊具の提供等の要望があったことが報告されました。
ウ この要望に対し、「ネットワーク検討会議」の対応として、1:現物の提供、2:寄附金等や事業活動として提供、3:人的支援の提供の他、4:仮設住宅にコミュニティ広場をつくり環境改善を提案する等知恵の提供もあること、また、単年度だけでなく4、5年程度又はそれ以上の中長期にわたる継続性のある支援が必要であること、さらに、要望のすべてに対応出来ない場合は、現地との話し合いの上、波及効果のある所にモデル的な支援を行うこと等多数の意見が提案されました。
エ 本協会からも、復興支援策として会員から提案されている、安藤忠雄先生から話のあった「鎮魂の森(公園)」建設や「サクラ100万本植樹計画」について紹介しました。
オ 今後、被災地等の地方公共団体を会員としている公園緑地協会が「ネットワーク検討会議」の窓口となり、被災地の地方公共団体及び参加団体との調整を図りながら、「ネットワーク検討会議」として具体的な支援活動を検討することになりました。
カ また、長期的な支援が必要となることから、公園緑地協会に専用ホームページを立ち上げ、それぞれの参加団体がリンクして情報の共有化を図ることとしました。
◇被災地の現地調査報告のホームページ
日本造園学会:http://www.landscapearchitecture.or.jp/dd.aspx?menuid=1258
公園緑地協会:http://www.posa.or.jp/outline/sub_jigyou_chousa_shinsai.html
この未曾有の大災害に対して、造園・環境緑化関係団体では、それぞれ様々な復興支援活動を準備していますが、その動きとしては、現在のところ、以下のとおりです。
1.当協会の被災会員に対する支援活動
(1) 協会では、会長等三役が被災会員のお見舞と激励のため現地に伺い、その後、顧問や林野庁に状況を説明して今後の対処についての協力をお願いしてきました。
(2) 理事会の決議により、当協会としては、甚大な被災会員5社園に対しては、協会から「お見舞金」贈呈及び年度会費の免除を実施する他、会員の皆様から義援金を募集することにしましたが、現在、2,191千円の義援金の拠出をいただいております。集まった義援金の配分等については7月の理事会で決定する予定になっています。
(3) 原発事故に係る補償に関しては、避難に伴う営業の損失や風評被害の賠償について、現在、政府の原子力損害賠償紛争審査会で検討中ですが、農林水産省でも、農林水産業等の原子力損害賠償請求を円滑に進めるため、関係県、農林水産業関係団体等からなる「東京電力福島原子力発電所事故に係る連絡会議」を設置しています。
(4) 当協会では、林野庁、連絡会議等の情報を逐次被災会員に提供するとともに、被災会員からの要望や情報を聴取し林野庁に伝える等林野庁と連携して被災会員に対する支援を続けて行くことにしています。
(5) 原発事故の発生に伴い、緑化木等の販売に係る風評被害の報告が協会に寄せられていますが、この度、林野庁から緑化木等の出荷に当たっての留意事項等としてQAが会員限定情報内で別掲しているとおり示されました。
2.造園・環境緑化関係団体の支援活動
(1) 造園・環境緑化関係団体による被災地の現地調査については、既に、日本造園学会や公園緑地協会で実施され、それぞれ報告(下記のURLで内容等が参照できます。)されています。
(2) 花と緑に係わる業界関係者等が連携協力して被災地域の復興活動事業を支援するため、造園関係団体が中心となった「(仮称)東日本大震災「花とみどり」の復興支援ネットワーク検討会議」及び花き関係の団体が中心となった「東日本大震災関連地域の花と緑による復旧・復興支援活動情報連絡会議」がそれぞれ立ち上げられています。
(3) このうち、造園関係団体が中心となった「ネットワーク検討会議」の検討状況については、
ア 参加団体が、それぞれの支援活動について情報交換をしました。
イ 地方公共団体からの具体的な支援要望を聴取したところでは、1:花苗、球根、肥料、土、スコップ、プランター等のガーデニング用品、2:街路樹や公園への苗木提供、3:サッカーボール等の提供、4:公園遊具の提供等の要望があったことが報告されました。
ウ この要望に対し、「ネットワーク検討会議」の対応として、1:現物の提供、2:寄附金等や事業活動として提供、3:人的支援の提供の他、4:仮設住宅にコミュニティ広場をつくり環境改善を提案する等知恵の提供もあること、また、単年度だけでなく4、5年程度又はそれ以上の中長期にわたる継続性のある支援が必要であること、さらに、要望のすべてに対応出来ない場合は、現地との話し合いの上、波及効果のある所にモデル的な支援を行うこと等多数の意見が提案されました。
エ 本協会からも、復興支援策として会員から提案されている、安藤忠雄先生から話のあった「鎮魂の森(公園)」建設や「サクラ100万本植樹計画」について紹介しました。
オ 今後、被災地等の地方公共団体を会員としている公園緑地協会が「ネットワーク検討会議」の窓口となり、被災地の地方公共団体及び参加団体との調整を図りながら、「ネットワーク検討会議」として具体的な支援活動を検討することになりました。
カ また、長期的な支援が必要となることから、公園緑地協会に専用ホームページを立ち上げ、それぞれの参加団体がリンクして情報の共有化を図ることとしました。
◇被災地の現地調査報告のホームページ
日本造園学会:http://www.landscapearchitecture.or.jp/dd.aspx?menuid=1258
公園緑地協会:http://www.posa.or.jp/outline/sub_jigyou_chousa_shinsai.html